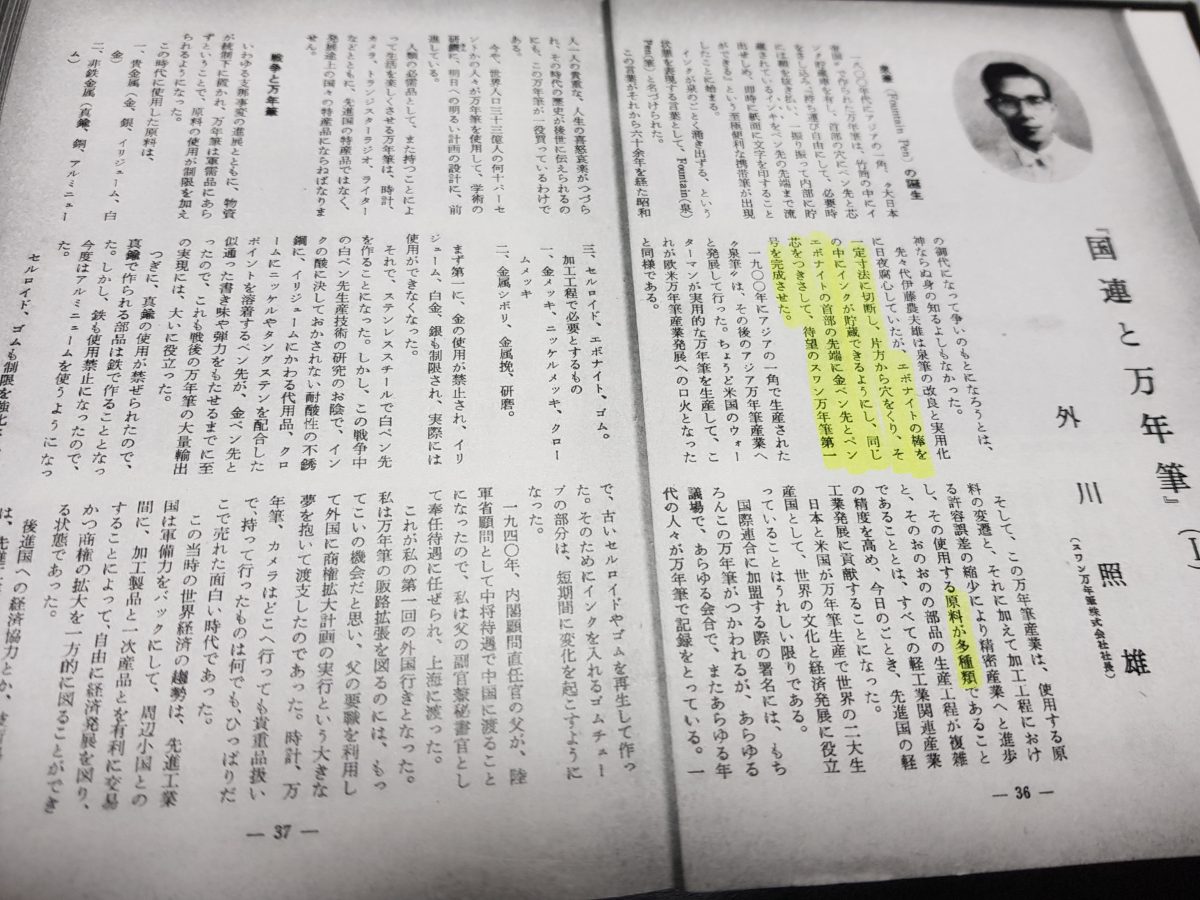日本の万年筆技術を海外に伝えた技術者 外川照雄(1966)「国連と万年筆」より
スワン万年筆株式会社の社長であった外川照雄氏による「国連と万年筆」を紹介する。この論文は半世紀以上前に、『国連』という雑誌に3回シリーズで掲載された。
- 外川照雄(1966)「国連と万年筆-1-」日本国際連合協会編,45(1)
- 外川照雄(1966)「国連と万年筆(その二)」日本国際連合協会編『国連』15(2)
- 外川照雄(1966)「国連と万年筆(その三)」日本国際連合協会編『国連』45(3)
(クリックで拡大)
外川照雄(1966)「国連と万年筆-1-」日本国際連合協会編,45(1),pp.36-41
外川氏はこの中で泉筆(Fountain Pen)の誕生と戦争下における万年筆の生産について述べる。
泉筆(Fountain Pen)の誕生
伊藤農夫雄がエボナイトの首部の先端に金ペン先とペン芯をさしてスワン万年筆第一号を完成させた。
1800年代にアジアの一家、“大日本帝国”で作られた万年筆は、竹筒の中にインク貯蔵庫を有し、首部の穴にペン先と芯をさし込み、『持ち運び自由にして、必要時には鞘を抜き払い、一振り振って内部に貯蔵されているインキをペン先の先端まで流出せしめ、即時に紙面に文字を印することができる』という至極便利な携帯筆が出現したことに始まる。
当時の万年筆は、国際連合への加盟の際の署名をはじめ、議場、会合で使われるのみならず、あらゆる国のあらゆる年代の人たちに使用され、万年筆は人類の必需品であり、世界の文化と経済発展に役立っていたと書かれている。当時の人たちのモノを書く道具=万年筆であったのだ。
また、以下に述べる戦争下での万年筆生産、戦前の外国との万年筆の貿易、中国との貿易についての記述は今や貴重な歴史資料であろう。
戦争下での万年筆生産
金の使用が禁止され、イリジウムや白金や銀も実質的に使用できなくなったということです。そのため、ステンレススチールを用いて白ペン先を作るようになった。
外川氏はこのときの白ペン先生産技術の研究がその後の、万年筆の大量輸出に大きく寄与したという。真鍮、鉄の使用が禁止され、アルミニウムを使用するようになった。さらに、セルロイドやゴムについても使用制限になり、セルロイドやゴムを再生して使用したらしい。
戦前の外国との万年筆の取引
インドや欧米系商社との取引は、非常に割り切った取り取引が多く、これについて「しょせん、島国育ちの浪花節的人情気をモットーにしていた日本人と、物質文明の先輩である欧米系人との間には、物の考え方の基本、法律、表現方法などで大きなギャップが存在していたのである。
中国との取引
至極のんびりしたもので、大まかな契約書で、別にむずかしい細則をつけるでもなく、そのくせ、一度約束したことは絶対に違えることなく、信頼と人情で終始した。
昨今の中国の印象とは大きく異なるものである。スワン万年筆による技術協力が、その後の中国の万年筆製造の発展に寄与していったようである。
外川照雄(1966)「国連と万年筆(その二)」日本国際連合協会編『国連』45(2)
このなかで外川氏は東京警備隊特殊技術班、GHQと万年筆産業、技術の革新と品質の向上、ビルマ政府納入と香港への技術協力について書いている。ここでは、戦後の占領下でいかに万年筆産業が復興していったのか、そして万年筆の技術革新と品質向上がどのように行われたのか、について着目してみたい。
1.GHQと万年筆産業の復興
万年筆産業における品質管理については、「GHQで招聘した品質管理の権威W.S.マギル氏およびH.M.サラソン氏が滞在し、緊急再建を必要とする通信機産業がこれをとり入れたことを契機として、日本の品質管理方式は急速に発展し、万年筆業界においても、1948年より規格の制定と輸出検査法が行われるようになった。この品質管理方式の中小企業の各部への浸透が、日本の工業発展に大いに寄与し、ひいては低開発国への技術協力にも一段と指導性を添えることになった。」と書かれている。
戦後日本の万年筆産業も他の産業と同様に品質管理方式の導入が発展の契機になったのである。
2.技術の革新と品質の向上
戦後10年の間に日本の万年筆は世界水準に到達した。
万年筆の製造技術は急激に向上し、その使用する原料も変革を伴った。永年使用されていたエボナイトやセルロイドに代わって、プラスチックが登場し、手動式機械は電動式におきかえられ、いまや電動式は全自動式にかわりつつある。
職人が細部の仕上げを手仕事で行っていた技術の重要性は、互換性、均一性と最小許容誤差での精密度を要求される量産製品の前には、いまやいにしえの語り草になとうとしている。
鉄は真鍮に代替され、真鍮はアルミニウムにおきかえられつつある。企業は常により高い品質の製品を生み出すために、貪欲な眼差しで、有利な材料を求め、新しい技術を求め、新しい考案を探している。
バフ研磨はバレル研磨に移り、真鍮に金鍍金(注,金メッキ)を行うよりも、アルミニウムを電解研磨してアノダイジングしたもののほうが色彩度、光沢度がよく永続性があり、商品価格を高めることになる。
戦後における品質管理方式の導入をはじめ、新素材の導入、手作業から電動へ変化など、戦後の万年筆製造をめぐる大きな環境変化を知る貴重な資料である。
外川照雄(1966)「国連と万年筆(その三)」日本国際連合協会編『国連』45(3)
外川氏が国連専門家に任命され、インドの万年筆産業への協力の経緯と最終報告の記録が掲載されている。外川氏が就任した国連専門家は、インド政府から国連に要請されたもので、インドの万年筆産業を世界水準に引き上げるために、インドの万年筆産業の現状分析、品質向上、生産合理化の方法を発見して、国連に実施案を提出することを任務としていた。この論文では、国連専門家の要請、国連査察団結成の背景、1963年国連査察団、そして最終報告と勧告について書かれている。
当時のインドの万年筆産業の現状
日本で明治時代に行っていたblowing lamp方式で燃えるランプの炎を長いパイプで吹いてペン先にペンポイントを付けている工場があると思うと、他の地域ではドイツから輸入した児童デューム溶着機を使用してアルゴンガス雰囲気中で一台当たり一日4,5千本のペンポイントをつけている。ステンレスペン先を一本、一本金槌でたたき、ペン先を手で作っていたかと思うと、一分間に180本のペン先を抜き、マークつけ、ハート穴あけを一台の機会で行っている所もある。70年間の各種製造工程の移り変りを映画で見ているのではないかと錯覚を起こすほどである。
このようなインドの万年筆産業の状況に対して、バフ研磨の工程をかえたり、小物のクリップを一本あて研磨しているのを二ダースあて研磨する器具を教えたり、ペン芯の溝の毛細管現象と空気穴の必要性を説いてつけさせるなど、多くの改善がなされた。外川氏らの技術協力はインドの工場で非常に喜ばれたそうである。
国連専門家の任を終えた外川氏は最後に次のように述べる。
おおくの方々のご指導ご協力にあずかり、このように任務を完遂できたことを、肝に銘じて感謝しつつ、低開発国援助に一層努力を続けてゆく覚悟でおります。
戦後、日本の万年筆技術を伝えたいという情熱をもったひとりの技術者がいたのである。